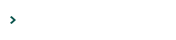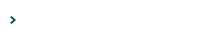第5 裁判所や自賠責・労災によるPTSDの判断
1 裁判所によるPTSDの判断基準
裁判所は、DSM-IV基準と、ICD-10基準を参考にして、
- 強烈な外傷体験
- 再体験症状(フラッシュバック)
- 回避症状
- 覚醒亢進症状
の4要件を厳格・厳密に適用していく運用で落ち着いています。
かつて、裁判所は、精神医学会から「PTSDのカオス(混沌)状態」と揶揄されるほど、安易にPTSDを認める傾向にありました。
ところが、そのような流れの中で、PTSDの病態に深く突っ込んだ検討をしたうえでPTSDを否定した平成14年7月17日の東京地裁のいわゆる鈴木判決 以降、東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁、横浜地裁の交通専門部による4庁協議会において協議した結果、最新の精神医学会での知見を参考にして、前記の判断 基準を定立しました。
2 自賠・労災・裁判所は、容易にはPTSDを認定しない
以上のとおり、自賠責保険・労災保険・裁判所によってPTSDの認定基準が定立されていますが、現実には、PTSDが認定されることはまずありません。現在、PTSDの認定は極めて狭き門になっています。
その理由は以下のとおりです。
(1)「強烈な外傷体験」の壁
PTSDの認定要件として、「強烈な外傷体験」をしたことが必要となります。この「強烈な外傷体験」とは具体的に どのような場合を言うのかについて、精神医学会において広く緩やかに捉える見解と狭く限定的に捉える見解とに分かれ激しい議論が展開されています。これを A基準論争と言います。
ところが、強烈な外傷体験を広く捉える見解ですら、交通外傷が一般的に強烈な外傷体験だと言えるかは疑問だ、とされており、ましてや、強烈な外傷体験は、拷問・テロ・強姦のような「例外的に著しく驚異的あるいは破局的出来事」を意味するというように限定的に解する見解からすれば、およそ交通外傷の大半のケースがこれに該当しない結果になります。
近時の裁判所は、この「強烈な外傷体験」の要件を厳格に適用し、「本件はこれに該当しない」「そもそもPTSDではない」として、大半の事例をこの第1関門で弾いている傾向が顕著です。
補足 「強烈な外傷体験」とは何かを具体的に検討するうえで無視できない有名判例
PTSDが争点になったわけではありませんが、「強烈な外傷体験」とは何かを具体的に検討するうえで無視できない有名な裁判例として、東京地裁平成15年7月24日の判決例があります。
事案は、家族での行楽帰りに渋滞の高速道路を運転中、飲酒運転のトラックに追突されて炎上し、車に 綴じ込まれた2人の娘(当時3歳と1歳)が、助けを求める叫び声、泣き声を間近に聞きながらも、両親は、燃え盛る火勢のため、なすすべもなく、ただ最愛の 娘達が目の前で焼け死んでいくのを見ているほかなかった、というおよそ普通でない想像を絶するような悲惨な事例でした。
当時の裁判所基準では、死亡慰謝料は死亡した本人と近親者の慰謝料の総額で1人当たり2000万円であったところ、この裁判例では、子供本人の死亡慰謝料 として1人あたり2600万円(2名で5400万円)、両親分として総額1600万円を認定しました。1人に換算すると総額3400万円の認定をしたこと になり、当時の裁判所基準を大幅に上回る高額な慰謝料の認定がなされました。
ところが、両親の慰謝料を判断するうえで、両親のPTSDは問題になりませんでした。それは両親がそもそもPTSDに罹患しておらず、そのような主張が両親からなされなかったからです。
本件事案は、「強烈な外傷体験」をどんなに狭く限定的に捉える精神科医であっても、文句なしに「例外的に著しく驚異的あるいは破局的出来事」であるとして、その要件を充足するケースです。ところが、ご両親は2人ともPTSDにはなりませんでした。
さらに、本件事案は、裁判所が認定したように「原告ら(両親)は、我が子の死
に直面して立ち直ることすら困難であっても不思議ではないにもかかわらず、今後このような悲惨な事故が二度と起きないようにするために社会に訴え掛けていくことを決意し、刑法改正の署名運動に取り組んで37万人を超える署名を集め、その結果、危険運転致死傷罪の成立をみるに至ったこと、さらに、それに満足することなく、全国を巡って交通安全についての講演を重ね、被告通運の従業員に対しても自らの働き掛けによって講演を行う等、本件事故による尊い犠牲を無駄にしないために交通事故防止の活動に身を捧げていること、そ れにもかかわらず、被告通運の社内で交通安全を推進すべき立場にある取締役の1人が、純然たる業務中でないとはいえ、原告らの被告通運の従業員に対する前 記講演のわずか3週間後に飲酒運転による追突事故を発生させるに至り、その結果、原告らに、我が子の死は何だったかのか、我が子の死を無駄にしないために 行ってきた運動も飲酒運転の撲滅に向けて効果を上げられなかったのではないか、という憤り、無念さをもたらしたことなどの事情も、慰謝料の算定に当たっては充分に考慮されなければならない」事案でした。それでもご両親らはPTSDにはなりませんでした。
我々は、本件事故から5年経過した頃、ある被害者の会の会合で、このご両親の講演を聴いたことがありました。ご主人は温厚で柔和な感じの方であり、奥さん は、暗い様子が微塵もなく、むしろ普通の人よりエネルギーに満ちている感じがしました。そして奥さんは、自分達が受けた心の傷や悲惨さを声高に主張される ことは一切なく、当日のテーマであった定期金賠償の論点についてしっかりとした説明をされておられました。
「人それぞれだ」「要は気の持ちようだ」と言ってしまえばそれまでです。他方、このご両親がこのような悲惨な事故でPTSDにならなったのだから、交通事 故の事案ではおよそPTSDは発症しないとまで言えないこともたしかです。しかし、この裁判例はあまりに有名で、交通事故裁判にかかわっている法曹関係者 の中でこの裁判例を知らない者はいません。従って、裁判所が「強烈な外傷体験」か否かを検討するうえで重要な参考資料のうちのひとつとしていることは否定 できません。
(2)「因果関係」の壁
さて、極めてハードルの高い、「強烈な外傷体験」の壁を通過したうえに、さらに「再体験症状(フラッシュバック)」「回避症状」「覚醒亢進症状」といった全ての壁を無事通過できたとしても、次に立ちはだかっている壁は「因果関係」の壁です。この因果関係の壁には2つあります。一つは、事故と発症との因果関係の壁であり、もう一つは症状残存との因果関係の壁です。
- 事故と発症との因果関係の有無では、たとえその精神症状が「強烈な外傷体験」が一因となっていることが認められる場合であっても、発症時期が遅すぎたり、発症時期は遅くないが事故以外の本人の素因や家庭環境や職場環境による影響が強いと疑われる場合は、ここで弾かれます。
- 症状残存との因果関係の有無では、たとえその精神症状が交通事故を主因として発症したことが認められる場合であっても、その発症日以降専門医による診療が全くないか時期に遅れ過ぎていたため、残存症状が日に日に憎悪している場合などは、ここで弾かれます。
※このように、PTSDについて事故との因果関係の有無が厳しく問われるのは、PTSDも非器質性精神障害(脳は物理的には全く壊れておらず、画像上の異常所見が全くない状態)であって、その発症や症状の残存(治らない)結果が、事故だけが単独の原因とは言い難く、被害者の環境的要因や被害者自身の素因などが複雑に関連し合って発症し残存するという本質的に多因性の障害という特質をもっているからです。
また、専門医による治療の有無が厳しく問われるのは、専門医による精神医学上適切な治療がなされたときは、概ね半年〜1年、長くとも2年〜3年で完治し、後遺症を残さないのが大半であり、持続的な人格変化を認める重篤な症状が残るのは極めて稀だからです。ですから、事故から2年経過しても症状が改善していない場合で、かつ専門医による治療がなされていない場合は、適切な治療を受けてないからだ、事故だけのせいじゃない、と判断されるのです。精神専門医による精神科的治療がなされていないものは、ここで弾かれるわけです。
(3) 後遺症という名の壁
さて、以上の壁を全て無事通過しても、次に「後遺症という名の壁」という高い壁が立ちはだかっています。すなわち、事故によってPTSDになり、しかも専 門医によって適切な治療が行われてきたことが認められても、それが一生涯治ることがない後遺症とは判断されない場合があります。
というのは、自賠責保険では、後遺障害は一生涯治癒しないか回復困難と認められる障害だけを等級評価の対象としているため、PTSDは、前述のとおり、概ね半年〜1年、長くとも2年〜3年で完治し、後遺症を残さないのが大半であり、持続的な人格変化を認める重篤な症状が残るのは極めて稀なケースとされているからです。
これまで数多くの高い壁を通過し、狭き門をくぐり抜けて来た、いわば選りすぐりの少数精鋭の「事故によるPTSD」も、そのうち治る、生涯続くものではない、としてその大半が弾かれるわけです。
(4)素因減額の壁
そして、「後遺症という名の壁」も通過して、事故に因る後遺障害としてのPTSDが認定されても、最後の最後に、裁判所によって素因減額されます。
PTSDも非器質性精神障害であって、その発症や症状の残存結果が、事故だけが単独の原因とは言い難く、被害者の環境的要因や被害者自身の素因などが複雑に関連し合って発症し残存するという本質的に多因性の障害という特質をもっていて、実際上も交通事故によってPTSDが発症するのは極めて稀なケースだからです。
裁判例では、総損害額から2割〜3割の範囲で減額されているのが通常です。
(5)まとめ
このように、PTSDは
- まず最初に、「強烈な外傷体験」の壁によって、「そもそもPTSDではない」として、その大半が弾かれ
- 次に、PTSDだとしても、「事故が原因で発症したものではない」として「因果関係」の壁によって弾かれ
- さらに、事故に因ってPTSDになったとしても、「そのうち治る」として「後遺症という名の壁」によって弾かれ
- やっとの思いで、事故に因ってPTSDの後遺症が残ったと認定されても、最後の仕上げ(?)として、「事故だけが原因でPTSDになったのではなく被害者固有の環境や素因も関与していた」として「素因減額」の壁によって賠償額が減額されます。
このように交通外傷において、PTSDは踏んだり蹴ったりの現状です。その現状を説明する理屈は色々ありますが、その最大の理由は、最新の精神科医学の知見からして、交通事故によってPTSDが発症することは極めて例外的であって、ましてや後遺症として残ることなど皆無に近い、という認識と現実にあります。
※ 臨床医は、まともな治療方法を習熟していないにもかかわず、安易にPTSDの診断を下して被害者やその家族に重病感を植えつけ、それが、ますます症状を悪化・慢性化させて治療を長期化させているとの内部批判がされているようです。
臨床医がPTSDの後遺症を診断しても、自賠・労災・裁判所はほとんど絶対と言っていいほどそれを否定します。その原因としては、正確にPTSDの診断が出来る専門医が極端に少ないという事情もありますが、より本質的には両者の目的が全く異なるからです。
臨床医は病気を治すのが使命です。そのためには治療漏れを回避するため、最悪の場合であるPTSDも視野に入れた治療をする必要性があります。ですからPTSDの診断要件も必然的に緩やかに解さざるを得なくなるのです。
これに対し、自賠責保険、労災保険、裁判所は、後遺障害にかかる賠償を審査する機関です。特に裁判所は、立証責任は被害者にあるとの法律上のルールに従 い、後遺障害の存否と程度を慎重に決定する機関です。曖昧な診断や根拠では高額となる後遺障害の賠償を強制的に命ずることは出来ないのです。
3 そもそもPTSDか否かは重要でない。
このように、交通外傷に因る後遺障害としてのPTSDが認定されることはほとんどないのですが、それでも、被害者の中には、事故後、憂鬱状態になったり、不安感や恐怖感が増悪したり、意欲低下を来したりする人が多くはありませんがいらっしゃいます。
重い症状の人では、幻覚・幻聴の症状が慢性化したり、解離性健忘といって自分が誰でどのような生活史を持っていたのか、すっかり忘れてしまったり、衝動行動、徘徊等の奇怪行動をとったりで、精神専門医による精神科的治療をされている方がおられます。
それらの精神症状をPTSDと呼ぶか否かは別にして、事故が原因で精神症状が発生したとして、裁判所によって外傷性神経症や不安神経症などの名で14級から12級の限度で労働能力喪失期間を5年〜10年として後遺障害が認められる場合があります。
ですから、そもそも損害の認定において、PTSDに罹患したか否かは重要ではありません。
重要なのは
- 本件事故に因って
- 被害者がいかなる精神的打撃を被り
- どのような精神症状となり
- そのために具体的どのような損害が発生したのか、
という事実の主張と立証をすることに尽きます。
そこで適正な後遺障害を認定を受けるため、冒頭のポイント記載の鉄則を遵守することが極めて重要となるのです